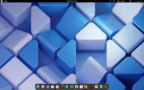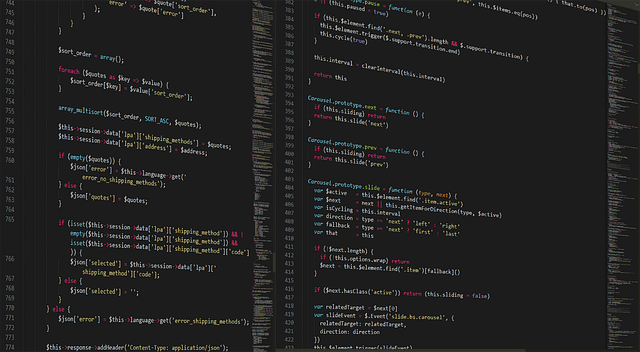
systemdは、従来のSysVinitに代わるinitシステムとしてFedoraやRHEL 7で導入され、現在では多くのディストリビューションに採用されている。しかし、その実態は単なるinitの代替にとどまらない。
systemdは、Linux系OSで使われるシステム管理デーモンの一つ。デーモン(daemon)は、バックグラウンドで常駐し、特定の処理やサービスを提供するプログラムだ。システムやアプリケーションの動作を支えるためには欠かせない。
systemdはログ管理(journald)、時刻同期(timesyncd)、ネットワーク設定(networkd)、サービス管理(systemctl)など、多数のコンポーネントを内包する巨大なソフトウェア群である。
こうした統合的かつ拡張的な設計は、Linuxのシンプルで柔軟な設計思想から逸脱しており、「UNIX哲学への明白な違反」として、導入当初から多くの開発者やユーザーによって懸念されてきた。
もはやsystemdは、initシステムという枠を越え、LinuxのコアAPIを再定義しようとする存在になっていると言っても過言ではない。
UNIX原則とKISSに対する背反
UNIX哲学では、「1つのプログラムは1つのことをうまくやる」ことが基本とされる。systemdはこの原則に正面から反している。
かつては分離されていた小さなユーティリティ群の機能を、1つのモノリシックなフレームワークに取り込んでしまった。その結果、システムの構成が不透明になり、障害発生時の切り分けが困難になる場面も少なくない。
特に問題となるのは、ログのバイナリ化(journald)である。従来のテキストベースのログと異なり、journalctlでなければ内容を簡単に確認できず、ツールの柔軟性が損なわれている。
また、標準的なPOSIX APIではなく、systemd独自のAPIや機能がアプリケーションに利用されるようになると、非systemd環境では互換性が失われるという問題が起きている。
Red Hatの影響とエゴによる設計支配
systemdの開発を主導するのはRed Hatであり、彼らが提供するRHELやその派生ディストロでは、systemdの導入が事実上強制されている。Fedoraを開発実験の場とし、安定したらRHELへ導入するというモデルは、確かに効率的だが、その一方で「Linux全体をRed Hatが牛耳っているのではないか」という不信感を抱かせる。
これは単なるinitの選定にとどまらず、Linuxの構成や振る舞いそのものを再定義しようとする政治的な動きとも取られかねない。Red Hatが主導するsystemdに多くのアプリケーションやサービスが依存するようになれば、他のinitシステムを使う選択肢はますます狭まり、自由で多様なオープンソース文化に逆行するとの批判も強まっている。
「学ばせない設計」とブラックボックス化
もう一つの懸念は、systemdが「学びにくい」構造を持つことだ。従来のinitスクリプトはシェルスクリプトとして記述され、ユーザーが容易に内容を理解し、修正・拡張することができた。
しかしsystemdのユニットファイルや内部構造は、慣れていないと読みにくく、動作の全容が把握しづらい。ログの確認もjournalctlという独自コマンドを使いこなさなければならない。
このような設計は、ユーザーがシステムの構成や動作原理を自分で学ぶ余地を狭め、Linuxが本来持っていた「透明性」と「自己解決能力」を失わせる要因となっている。背景には、デスクトップ指向の「コマンドライン忌避」文化の台頭があり、CLIを中心とした文化圏との断絶が進んでいる。
技術的便利さとロックインの代償
確かに、systemdには多くの利点がある。起動の並列化による高速化、systemctlによる統一されたサービス管理、タイマー機能など、従来のinitシステムでは難しかった機能が標準で提供されるようになった。企業ユースやデスクトップ用途においては、大きなメリットといえる。
しかし、これらの便利さはsystemdに過剰に依存する構造を生み、他のinitシステムでは代替困難な状況を作り出してしまった。
たとえば、GNOME や Flatpak といったソフトウェアが logind や timedated などのsystemdコンポーネントを前提とするようになると、非systemd環境での動作が難しくなる。こうして、選択の自由が実質的に失われるという「ロックイン」問題が深刻化している。
Linux文化の今後と選択肢の価値
systemdは、initの近代化という目的を越えて、Linux全体を「再設計」しようとする力を持ち始めている。その結果、「自由で分散型」というLinuxの原点が脅かされているのではないか、という疑念が拭えない。systemdに異議を唱えるディストリビューション(Devuan、Artixなど)は、単なる技術的反抗ではなく、文化的・思想的な抵抗運動として存在しているとも言える。
今後、Linuxが多様性と選択肢を保ち続けるためには、systemdに依存しない選択肢の維持と発展が不可欠だ。OpenRC、runit、s6、あるいは従来のSysVinitといった代替手段も、改めて再評価されるべきである。systemdにある問題を知らないユーザーも多いが「便利だからいい」と流されるばかりでなく、「自分で選べる自由」を守る姿勢を大切にしよう。